アイデアコンテスト紹介
夢と頭の運動会
1969年7月、狭山製作所(現、埼玉製作所狭山工場)恒例の運動会の1種目である仮装行列に、巨大な"球形の演(だ)し物"が登場した。その細い鋼板を篭状に編んだ直径約5mの球形の中には人が乗り込み、N600のエンジンを操作していた。この奇妙な物体を見た社長の本田宗一郎が、
「これは面白い。これこそHondaの夢と頭の運動会だ」
と喜んだ。
この一言がきっかけとなり、翌1970年にはアイディアコーナーが独立した形でアイデアコンテスト(以降、アイコン)が誕生し、全社的行事へと発展していった。
「アイコンは面白いからやるんだ。しかし、これをやるには、金がかかる。だから一生懸命働こう」
と、本田は1970年3月、鈴鹿サーキットで開催された第1回大会で語っている。
1971年10月に開催されたアイコン第2回大会から第6回大会までの審査員を務めた、森政弘・東京工業大学名誉教授は、
「『アイコンは技術開発のためにやっているのではない』という本田さんの一言が1番印象に残っている」
と語る。
アイコンは仕事ではなく、遊びである。遊びとは、やらされているという気持ちのない状態。まさに、人間らしい気持ちであり、自発性を大事にしている状態である。
Hondaでは、仕事と遊びは、それぞれ平等に考えられており、仕事をするときは仕事に集中し、遊ぶときは、思いっ切り遊ぶ。が、結果として遊びが仕事の、仕事が遊びの良い手段となり、相乗効果が現れるのだ。それは1973年9月に朝霞テックで開催された第4回アイコンにおける、本田の次のようなあいさつにも表れている。
「今日1日、楽しい思いをさせてもらってありがとう。今、アイコンを終わって、何とも言えないほほ笑みが次から次へとわいてくる。人生において、こうした静かな感動、大きな興奮が続いたら、どんなに良いだろうかと思わずにはいられない。
わが社がCVCCを開発して以来、『GMやフォードにできなかったものが、どうしてHondaにできるのか』と、よく聞かれ、そのたびに返事に困った。しかし、それはこう答えるべきなのだと今、思う。われわれは、このアイコンに代表されるような楽しい思い、楽しい苦労をしているからだと。
私は今後、こういう質問を受けたときは、
『アイコンへ来ていただきたい。われわれのCVCCがどうして生まれたか、ご理解いただけるでしょう』と答えたい」。
アイコンの目的は、普段は与えられた仕事をこなすだけになりがちな若手従業員が、仕事を離れた余暇に、枠にとらわれない自由な発想で、日ごろ抱いている"夢"を具現化することにある。アイコンは、商品化や実用化という考えから離れて、つまり、役に立つとか役に立たないと考える前に、つくってみることから始まる。そこには、重い物なら文鎮にはなるさという、形にすれば何かしら絶対に役に立つぞ、という本田独特のおおらかさ、面白がり方が原点にある。
さらに、商品化することが狙いではなく、あくまでも遊びであるために、出品された作品は、大会終了後、すべて廃棄してしまう。
Hondaで働く多くの従業員の通常の仕事は、製品の一部を受け持つライン作業が中心である。それに対してアイコンは、最初から最後まで自分たちの手でつくり上げられる。しかもそれが、夢を具現化することを目的としているのだから、喜びもひとしおである。
さらに、さまざまな人間が集まってチームを組むことにより、どんどんアイデアが広がっていく。意見が食い違ったり衝突することもあるかも知れないが、新しい仲間ができ、お互いに考え、創造することの楽しさをみんなで分かち合う。
この楽しさを味わうことこそ、人間が原点に戻ることができる瞬間なのである。
埼玉製作所(現、埼玉製作所和光工場)在籍時代に、10作品以上のアイコン作品をつくった経験を持つ塚本隆一(現、常任顧問)は言う。
「1970年の第1回大会で、僕とともにオーバルホイーラーに乗ったオヤジさん(本田のこと)は、ユーモラスな乗り心地を心から楽しんでいらっしゃった。しかし、車輪を楕円に変形させただけの単純なメカニズムを説明すると、みるみるうちに、がっかりした表情になり、"ケッ"という顔で降りてしまわれました。あまりにも単純なメカニズムが気に食わなかったらしい。でも、われわれにとって、自分でつくったものが完成し、ましてや動くなんて、初めての体験であり、楽しかったし、純粋にうれしかった。
また、アイコン大会では、自分の想像を超えた素晴らしい作品を目の当たりにし、刺激され、競争心がむくむくと頭をもたげてきて、大会が終わるとすぐに次回の企画を考えたものです。自分の知らない技術を調べたり、メンバーから教えてもらうのは大変だったが、とにかく楽しかった。本番1カ月前からは会社に泊まり、ほとんど徹夜状態でした。そうしているうちに、初出場のころの純粋な日曜大工的な喜びから、次第にアイコンにのめり込み、世の中にないものをつくろうと、どんどん欲求レベルが高くなっていきました。
アイコンで学んだことは、アイデアを具現化することの難しさと、限られた時間の中で、できる限りのことをやり尽くすことの重要性です。手を抜くと本番で必ず後悔しました。仕事を通じて、このことが分かるのは随分後になってからでした。アイコンを通して、楽しみや苦しみなど、いろいろなことを圧縮して経験できました」。
アイコンは第1回から第5回(1975年5月)までは、会社の行事として運営された。第1回大会の応募件数は996件、第2回大会は1170件、第3回大会は4578件と、次第に盛んになり応募件数も増えてきた。
反面、遊び心がなくなり、実用的な作品が多く、面白味がなくなってきた。また、力が入りすぎて、課ごと、事業所ごとの競争のような形となり、当初の自発性を大事にするという考え方から少しずれてしまった。
そのため、第6回大会からは、アイコンの運営はレクリエーション組織に委ねられたが、会社もバックアップを惜しまなかった。各事業所に、作品製作のために自由に使える工作機械を備えた工作室をつくり、制作費もレクリエーション費用で賄うことにした。
一方、開催回数を重ねるにつれて、アイデアが出尽くし、マンネリ化したため、参加する側も、見て楽しむ側も喜びが感じられなくなってきた。そこで、主催者側は、毎年の開催を2年、または3年に1回としたり、アイデアを具現化する前に、まず、模型による事前審査を行い、徹底的にアイデアの質を高めようとした。
しかし、こうしたアイコン活性化対策が、自由な発想に枠をはめる結果となり、アイコンの本来の姿とは離れてしまった。
1991年11月の12回大会は規模が縮小され、1993年の13回大会では『ナンバーワン大会』(事業所ごとに選ばれた作品の中でナンバーワンを決める大会)を開催することなく中止となった。
折からのバブル崩壊により、企業体質の強化を余儀なくされた結果、レクリエーション費用の大幅な削減が行われたのだ。アイコン関連費用も例外ではなかった。
その後、アイコンは再開されることなく、今日に至っている。
アイコンが形骸化し始めた1980年ごろからは、米国のホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチャリングにおける4輪車工場着工など、海外での生産拠点展開が本格化する時期でもあった。アイコンを経験したことにより自信を持ち、仲間のネットワークを広げた若者たちの中には、海外の新しい工場づくりに携わり、現地のアソシエイトとともに、ものづくりを進める者も出てきた。
『楽しもう。この手で夢をつくってみよう』というアイコンは、結果として、海外の事業展開にも少なからず貢献したといえる。
アイコンを通して従業員が得たものは、『夢を見ることは楽しいが、夢をアイデアに変えて、自分たちの手で実現していくことはもっと楽しい』ということの実感である。
そして、Hondaの歴史に、『モノづくりは人づくりにつながる』という事実を残していった。
出典:Honda #本田宗一郎 #藤澤武夫 #アイデアコンテスト
Видео アイデアコンテスト紹介 канала ホンダホビーチャンネル
1969年7月、狭山製作所(現、埼玉製作所狭山工場)恒例の運動会の1種目である仮装行列に、巨大な"球形の演(だ)し物"が登場した。その細い鋼板を篭状に編んだ直径約5mの球形の中には人が乗り込み、N600のエンジンを操作していた。この奇妙な物体を見た社長の本田宗一郎が、
「これは面白い。これこそHondaの夢と頭の運動会だ」
と喜んだ。
この一言がきっかけとなり、翌1970年にはアイディアコーナーが独立した形でアイデアコンテスト(以降、アイコン)が誕生し、全社的行事へと発展していった。
「アイコンは面白いからやるんだ。しかし、これをやるには、金がかかる。だから一生懸命働こう」
と、本田は1970年3月、鈴鹿サーキットで開催された第1回大会で語っている。
1971年10月に開催されたアイコン第2回大会から第6回大会までの審査員を務めた、森政弘・東京工業大学名誉教授は、
「『アイコンは技術開発のためにやっているのではない』という本田さんの一言が1番印象に残っている」
と語る。
アイコンは仕事ではなく、遊びである。遊びとは、やらされているという気持ちのない状態。まさに、人間らしい気持ちであり、自発性を大事にしている状態である。
Hondaでは、仕事と遊びは、それぞれ平等に考えられており、仕事をするときは仕事に集中し、遊ぶときは、思いっ切り遊ぶ。が、結果として遊びが仕事の、仕事が遊びの良い手段となり、相乗効果が現れるのだ。それは1973年9月に朝霞テックで開催された第4回アイコンにおける、本田の次のようなあいさつにも表れている。
「今日1日、楽しい思いをさせてもらってありがとう。今、アイコンを終わって、何とも言えないほほ笑みが次から次へとわいてくる。人生において、こうした静かな感動、大きな興奮が続いたら、どんなに良いだろうかと思わずにはいられない。
わが社がCVCCを開発して以来、『GMやフォードにできなかったものが、どうしてHondaにできるのか』と、よく聞かれ、そのたびに返事に困った。しかし、それはこう答えるべきなのだと今、思う。われわれは、このアイコンに代表されるような楽しい思い、楽しい苦労をしているからだと。
私は今後、こういう質問を受けたときは、
『アイコンへ来ていただきたい。われわれのCVCCがどうして生まれたか、ご理解いただけるでしょう』と答えたい」。
アイコンの目的は、普段は与えられた仕事をこなすだけになりがちな若手従業員が、仕事を離れた余暇に、枠にとらわれない自由な発想で、日ごろ抱いている"夢"を具現化することにある。アイコンは、商品化や実用化という考えから離れて、つまり、役に立つとか役に立たないと考える前に、つくってみることから始まる。そこには、重い物なら文鎮にはなるさという、形にすれば何かしら絶対に役に立つぞ、という本田独特のおおらかさ、面白がり方が原点にある。
さらに、商品化することが狙いではなく、あくまでも遊びであるために、出品された作品は、大会終了後、すべて廃棄してしまう。
Hondaで働く多くの従業員の通常の仕事は、製品の一部を受け持つライン作業が中心である。それに対してアイコンは、最初から最後まで自分たちの手でつくり上げられる。しかもそれが、夢を具現化することを目的としているのだから、喜びもひとしおである。
さらに、さまざまな人間が集まってチームを組むことにより、どんどんアイデアが広がっていく。意見が食い違ったり衝突することもあるかも知れないが、新しい仲間ができ、お互いに考え、創造することの楽しさをみんなで分かち合う。
この楽しさを味わうことこそ、人間が原点に戻ることができる瞬間なのである。
埼玉製作所(現、埼玉製作所和光工場)在籍時代に、10作品以上のアイコン作品をつくった経験を持つ塚本隆一(現、常任顧問)は言う。
「1970年の第1回大会で、僕とともにオーバルホイーラーに乗ったオヤジさん(本田のこと)は、ユーモラスな乗り心地を心から楽しんでいらっしゃった。しかし、車輪を楕円に変形させただけの単純なメカニズムを説明すると、みるみるうちに、がっかりした表情になり、"ケッ"という顔で降りてしまわれました。あまりにも単純なメカニズムが気に食わなかったらしい。でも、われわれにとって、自分でつくったものが完成し、ましてや動くなんて、初めての体験であり、楽しかったし、純粋にうれしかった。
また、アイコン大会では、自分の想像を超えた素晴らしい作品を目の当たりにし、刺激され、競争心がむくむくと頭をもたげてきて、大会が終わるとすぐに次回の企画を考えたものです。自分の知らない技術を調べたり、メンバーから教えてもらうのは大変だったが、とにかく楽しかった。本番1カ月前からは会社に泊まり、ほとんど徹夜状態でした。そうしているうちに、初出場のころの純粋な日曜大工的な喜びから、次第にアイコンにのめり込み、世の中にないものをつくろうと、どんどん欲求レベルが高くなっていきました。
アイコンで学んだことは、アイデアを具現化することの難しさと、限られた時間の中で、できる限りのことをやり尽くすことの重要性です。手を抜くと本番で必ず後悔しました。仕事を通じて、このことが分かるのは随分後になってからでした。アイコンを通して、楽しみや苦しみなど、いろいろなことを圧縮して経験できました」。
アイコンは第1回から第5回(1975年5月)までは、会社の行事として運営された。第1回大会の応募件数は996件、第2回大会は1170件、第3回大会は4578件と、次第に盛んになり応募件数も増えてきた。
反面、遊び心がなくなり、実用的な作品が多く、面白味がなくなってきた。また、力が入りすぎて、課ごと、事業所ごとの競争のような形となり、当初の自発性を大事にするという考え方から少しずれてしまった。
そのため、第6回大会からは、アイコンの運営はレクリエーション組織に委ねられたが、会社もバックアップを惜しまなかった。各事業所に、作品製作のために自由に使える工作機械を備えた工作室をつくり、制作費もレクリエーション費用で賄うことにした。
一方、開催回数を重ねるにつれて、アイデアが出尽くし、マンネリ化したため、参加する側も、見て楽しむ側も喜びが感じられなくなってきた。そこで、主催者側は、毎年の開催を2年、または3年に1回としたり、アイデアを具現化する前に、まず、模型による事前審査を行い、徹底的にアイデアの質を高めようとした。
しかし、こうしたアイコン活性化対策が、自由な発想に枠をはめる結果となり、アイコンの本来の姿とは離れてしまった。
1991年11月の12回大会は規模が縮小され、1993年の13回大会では『ナンバーワン大会』(事業所ごとに選ばれた作品の中でナンバーワンを決める大会)を開催することなく中止となった。
折からのバブル崩壊により、企業体質の強化を余儀なくされた結果、レクリエーション費用の大幅な削減が行われたのだ。アイコン関連費用も例外ではなかった。
その後、アイコンは再開されることなく、今日に至っている。
アイコンが形骸化し始めた1980年ごろからは、米国のホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチャリングにおける4輪車工場着工など、海外での生産拠点展開が本格化する時期でもあった。アイコンを経験したことにより自信を持ち、仲間のネットワークを広げた若者たちの中には、海外の新しい工場づくりに携わり、現地のアソシエイトとともに、ものづくりを進める者も出てきた。
『楽しもう。この手で夢をつくってみよう』というアイコンは、結果として、海外の事業展開にも少なからず貢献したといえる。
アイコンを通して従業員が得たものは、『夢を見ることは楽しいが、夢をアイデアに変えて、自分たちの手で実現していくことはもっと楽しい』ということの実感である。
そして、Hondaの歴史に、『モノづくりは人づくりにつながる』という事実を残していった。
出典:Honda #本田宗一郎 #藤澤武夫 #アイデアコンテスト
Видео アイデアコンテスト紹介 канала ホンダホビーチャンネル
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
 キャンプに夜食堂の豚汁
キャンプに夜食堂の豚汁 炭焼きハンバーグさわやかで【げんこつハンバーグ】を食べました
炭焼きハンバーグさわやかで【げんこつハンバーグ】を食べました ホンダカブF型梱包ダンボール箱の紹介
ホンダカブF型梱包ダンボール箱の紹介 TL125フューエルタンクラベル製作しました
TL125フューエルタンクラベル製作しました モンキーZ50Aの純正部品情報(統合)(価格)(廃盤)
モンキーZ50Aの純正部品情報(統合)(価格)(廃盤) ハンターカブ で行くSSTR「仲間のサポート珍道中!」
ハンターカブ で行くSSTR「仲間のサポート珍道中!」 HONDA RA273TAMIYA 1/12プラモデルの紹介
HONDA RA273TAMIYA 1/12プラモデルの紹介 『さいとうフルーツ』青果店の大人気フルーツジュース
『さいとうフルーツ』青果店の大人気フルーツジュース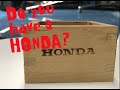 ホンダの酒升紹介
ホンダの酒升紹介 ローラースルーGOGOのケーブルクリップ製作
ローラースルーGOGOのケーブルクリップ製作 HondaTL125Iイーハトーブのシートレストア紹介
HondaTL125Iイーハトーブのシートレストア紹介 HONDA T360 EBLO 1/43 の紹介
HONDA T360 EBLO 1/43 の紹介 本田宗一郎生誕100年遺品展の紹介
本田宗一郎生誕100年遺品展の紹介 スーパーカブ用タイヤ交換作業台の作り方
スーパーカブ用タイヤ交換作業台の作り方 ホンダ発電機EX400 GENERATORの紹介
ホンダ発電機EX400 GENERATORの紹介 行列の出来る炭焼きレストラン【さわやか】
行列の出来る炭焼きレストラン【さわやか】 木曽御嶽山復興ツーリング紹介
木曽御嶽山復興ツーリング紹介 Honda MT250 スティーブマックィーンエルシノアCR250SteveMcQueen ELSINORE
Honda MT250 スティーブマックィーンエルシノアCR250SteveMcQueen ELSINORE ハヤシライス、カツハヤシは洋食屋千楽
ハヤシライス、カツハヤシは洋食屋千楽 鍋田記念・富士山ヒルクライムラン2018
鍋田記念・富士山ヒルクライムラン2018