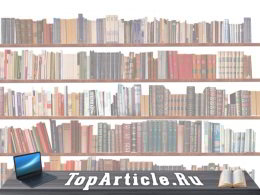「親ができることはやってあげたい、でも私もメンタルやばいなって」不登校に向き合う親たちの苦悩 語り合える場は少なく
不登校の子どもたちの数は昨年度、全国でおよそ34万6000人と、11年連続で過去最多を更新した。”我が子の不登校”に直面する親も当然増えていることになるが、親自身が抱える悩みやつらさに焦点があたることは少ない。福岡市で活動する「親の会」を取材した。
次男の不登校きっかけに親の会を立ち上げた
不登校の子どもと向き合う”親の会”が福岡市にある。東区で活動する「不登校・行き渋り等親の会」。月に1回集まって、子どもの状況や自分自身の悩みなどを共有している。中学1年の娘と小学4年の不登校の息子を持つ母親
「親ができることはやってあげたいんですけどそれをやっている自分の気力がちょっと結構もたなくなってきて私もメンタルやばいなと思って」代表の舩山郁乃さん(48)が会を立ち上げたのは6年前。次男の不登校がきっかけだった。舩山郁乃さん
「息子が3人います。今、高校2年生と中学1年生と小学3年生。3人とも不登校の時期がありました。3人とも不登校になった時は本当に悩んで寝込みました。で、この場に救われたなという感じなんですけど」今は、中学1年になった次男と小学3年の三男、不登校の2人の子どもと向き合っている。
不登校の子ども 11年連続で過去最多 向き合う親も増えている
文部科学省によると、不登校になっている児童・生徒の数は昨年度、全国でおよそ34万6000人。11年連続で過去最多を更新し続けている。福岡県内に住む不登校の子供の数も過去最多のおよそ1万8000人になった。不登校の児童や生徒が増加の一途をたどる中、その子どもたちと向き合う保護者の数も増えている。
「なんで生きていないといけないの?」娘の言葉 親はどうすれば
2月11日に開催された交流会には、これまでで最も多い16人の保護者が参加した。不登校の子を持つ母親
「情緒は安定してきて家の中でも明るくすごせるようになってきたけど、学校に行くのはちょっとまだかな、と親から見てると思うし、本人はクラス替えがあって4月からは行きたいとは言っているんだけど罪悪感から言っているかもしれないから」不登校の子を持つ母親
「学校に行く行かないの朝、バトルがきつかったんですけど、もう”行かない”って決めたらこっちもちょっと楽になって、やっと穏やかな日々が過ごせているかな。やっぱり行く行かないって悩んでいる時期が一番きつかったかな」子どもが不登校になったいきさつは様々だが、「不登校の子どもと向き合っている」という境遇は同じ。この日初めて参加した母親は、不登校の娘に「なんで生きていないといけないの?」と聞かれ対応に悩んでいると口にした。それを聞いていた別の母親が静かに?どんなふうに?自らの経験を話す。不登校の子を持つ母親
「うちの子も『なんで生きてないといけないの』って言われた時があってすごくつらかったです。でもそれってやっぱり言葉が出ているのはいいことだと思わないといけないと思いました。すごくつらいですよね。すごくつらいけどそれが言えなかったら生きることをやめてしまうかもしれないと思ったら、子供の笑顔を守って生きているだけでそれを良しとしないといけないんだろうなって」
硬い表情、だんだん柔らかに
始めは硬い表情だった初参加の親たちも、胸の内にとどめていた悩みを話し、そして聞くことによって、徐々に表情が柔らかくなっていく。初めて参加した母親
「本当に私も夫もどうしたらいいかわからないところがあって、スクールカウンセラーとかいろんな先生とかに会った時には相談はできるけど、やっぱり『もっとこういうのあるよ』とか積極的に相談できる場というのが、こういう会があって本当に本当にいいなと思いました」初めて参加した母親「学校には行けてないけど『ちょっとした変化とかがあることに目を向けて元気にならなきゃっ』ていつも焦ってしまうけど、『もうしょうがないんだ』と思ってまた自分を思いつめてしまうから、子どもと一緒に元気になっていこうかなと思いました」
「渦中にいると不安と悩みでいっぱいになってしまう」
会を立ち上げた舩山郁乃さんによると、不登校の子どもと向き合っていると、親自身も気持ちに波が出てくるという。集まって話し耳を傾けることで、そこを軽くしたい、と話した。舩山郁乃さん
「親も子どもも元気でさえいればなんとか道は開けていくと思うので。でもやっぱりなかなか渦中にいると不安と悩みでいっぱいになって余裕がなくなってしまう。そういう気持ちの余裕を取り戻す、気持ちが少し軽くなる、そういう風になっていけばいいなと思います」
”親に責任があるのではない”周囲の理解も大切
孤立しがちな不登校の子どもと親たちに、私たちはどのような支援ができるのだろうか。支援のあり方を研究する福岡県立大学の原田直樹准教授は「不登校の子供と親には多様な生き方があるということを、周囲が正しく理解することが大切だ」と話す。福岡県立大学・看護学部 原田直樹准教授
「親を支援する場が本当に少ないんですよね。いわゆる相談に行ってカウンセリングを受けることもできますけれど、それ以外に集える場というのは親の会が数か所にあるだけで、それもどこにでもあるわけではないですから、親を支える場は非常に少ないです。我々周りの人間は”親に責任があるのではない”ということと、子どもと親に対して”多様な生き方ができるんだ”ということをちゃんと認識して理解してあげることが重要かなと思います」原田教授によると、不登校の原因は多様で分からないことが多い。しかし、「不登校は親のせい」という偏見に苦しめられている親は多い。福岡市の「不登校・行き渋り等親の会」は、親たちにとって大切な「心の居場所」となっている。問題に直面する親たちを社会が支援するしくみが必要だ。RKB毎日放送 記者 植高貴寛
詳細は NEWS DIG でも!↓
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/1747002
Видео 「親ができることはやってあげたい、でも私もメンタルやばいなって」不登校に向き合う親たちの苦悩 語り合える場は少なく канала RKB毎日放送NEWS
次男の不登校きっかけに親の会を立ち上げた
不登校の子どもと向き合う”親の会”が福岡市にある。東区で活動する「不登校・行き渋り等親の会」。月に1回集まって、子どもの状況や自分自身の悩みなどを共有している。中学1年の娘と小学4年の不登校の息子を持つ母親
「親ができることはやってあげたいんですけどそれをやっている自分の気力がちょっと結構もたなくなってきて私もメンタルやばいなと思って」代表の舩山郁乃さん(48)が会を立ち上げたのは6年前。次男の不登校がきっかけだった。舩山郁乃さん
「息子が3人います。今、高校2年生と中学1年生と小学3年生。3人とも不登校の時期がありました。3人とも不登校になった時は本当に悩んで寝込みました。で、この場に救われたなという感じなんですけど」今は、中学1年になった次男と小学3年の三男、不登校の2人の子どもと向き合っている。
不登校の子ども 11年連続で過去最多 向き合う親も増えている
文部科学省によると、不登校になっている児童・生徒の数は昨年度、全国でおよそ34万6000人。11年連続で過去最多を更新し続けている。福岡県内に住む不登校の子供の数も過去最多のおよそ1万8000人になった。不登校の児童や生徒が増加の一途をたどる中、その子どもたちと向き合う保護者の数も増えている。
「なんで生きていないといけないの?」娘の言葉 親はどうすれば
2月11日に開催された交流会には、これまでで最も多い16人の保護者が参加した。不登校の子を持つ母親
「情緒は安定してきて家の中でも明るくすごせるようになってきたけど、学校に行くのはちょっとまだかな、と親から見てると思うし、本人はクラス替えがあって4月からは行きたいとは言っているんだけど罪悪感から言っているかもしれないから」不登校の子を持つ母親
「学校に行く行かないの朝、バトルがきつかったんですけど、もう”行かない”って決めたらこっちもちょっと楽になって、やっと穏やかな日々が過ごせているかな。やっぱり行く行かないって悩んでいる時期が一番きつかったかな」子どもが不登校になったいきさつは様々だが、「不登校の子どもと向き合っている」という境遇は同じ。この日初めて参加した母親は、不登校の娘に「なんで生きていないといけないの?」と聞かれ対応に悩んでいると口にした。それを聞いていた別の母親が静かに?どんなふうに?自らの経験を話す。不登校の子を持つ母親
「うちの子も『なんで生きてないといけないの』って言われた時があってすごくつらかったです。でもそれってやっぱり言葉が出ているのはいいことだと思わないといけないと思いました。すごくつらいですよね。すごくつらいけどそれが言えなかったら生きることをやめてしまうかもしれないと思ったら、子供の笑顔を守って生きているだけでそれを良しとしないといけないんだろうなって」
硬い表情、だんだん柔らかに
始めは硬い表情だった初参加の親たちも、胸の内にとどめていた悩みを話し、そして聞くことによって、徐々に表情が柔らかくなっていく。初めて参加した母親
「本当に私も夫もどうしたらいいかわからないところがあって、スクールカウンセラーとかいろんな先生とかに会った時には相談はできるけど、やっぱり『もっとこういうのあるよ』とか積極的に相談できる場というのが、こういう会があって本当に本当にいいなと思いました」初めて参加した母親「学校には行けてないけど『ちょっとした変化とかがあることに目を向けて元気にならなきゃっ』ていつも焦ってしまうけど、『もうしょうがないんだ』と思ってまた自分を思いつめてしまうから、子どもと一緒に元気になっていこうかなと思いました」
「渦中にいると不安と悩みでいっぱいになってしまう」
会を立ち上げた舩山郁乃さんによると、不登校の子どもと向き合っていると、親自身も気持ちに波が出てくるという。集まって話し耳を傾けることで、そこを軽くしたい、と話した。舩山郁乃さん
「親も子どもも元気でさえいればなんとか道は開けていくと思うので。でもやっぱりなかなか渦中にいると不安と悩みでいっぱいになって余裕がなくなってしまう。そういう気持ちの余裕を取り戻す、気持ちが少し軽くなる、そういう風になっていけばいいなと思います」
”親に責任があるのではない”周囲の理解も大切
孤立しがちな不登校の子どもと親たちに、私たちはどのような支援ができるのだろうか。支援のあり方を研究する福岡県立大学の原田直樹准教授は「不登校の子供と親には多様な生き方があるということを、周囲が正しく理解することが大切だ」と話す。福岡県立大学・看護学部 原田直樹准教授
「親を支援する場が本当に少ないんですよね。いわゆる相談に行ってカウンセリングを受けることもできますけれど、それ以外に集える場というのは親の会が数か所にあるだけで、それもどこにでもあるわけではないですから、親を支える場は非常に少ないです。我々周りの人間は”親に責任があるのではない”ということと、子どもと親に対して”多様な生き方ができるんだ”ということをちゃんと認識して理解してあげることが重要かなと思います」原田教授によると、不登校の原因は多様で分からないことが多い。しかし、「不登校は親のせい」という偏見に苦しめられている親は多い。福岡市の「不登校・行き渋り等親の会」は、親たちにとって大切な「心の居場所」となっている。問題に直面する親たちを社会が支援するしくみが必要だ。RKB毎日放送 記者 植高貴寛
詳細は NEWS DIG でも!↓
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/1747002
Видео 「親ができることはやってあげたい、でも私もメンタルやばいなって」不登校に向き合う親たちの苦悩 語り合える場は少なく канала RKB毎日放送NEWS
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
21 февраля 2025 г. 15:14:21
00:06:22
Другие видео канала