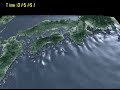- Популярные видео
- Авто
- Видео-блоги
- ДТП, аварии
- Для маленьких
- Еда, напитки
- Животные
- Закон и право
- Знаменитости
- Игры
- Искусство
- Комедии
- Красота, мода
- Кулинария, рецепты
- Люди
- Мото
- Музыка
- Мультфильмы
- Наука, технологии
- Новости
- Образование
- Политика
- Праздники
- Приколы
- Природа
- Происшествия
- Путешествия
- Развлечения
- Ржач
- Семья
- Сериалы
- Спорт
- Стиль жизни
- ТВ передачи
- Танцы
- Технологии
- Товары
- Ужасы
- Фильмы
- Шоу-бизнес
- Юмор
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)は本当にに科学的に正しい映像だったのか?
下記のブログをnotebooklmで動画化してみました。
notebooklmが生成した動画と解説音声、ストーリーは概ね正しいですが勝手な解釈や端折った部分が散見していますので詳細は下記のブログ内容でご確認ください。
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)①
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/08/28/201509
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)②
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/11/105538
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)③
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/13/153234
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)④
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/17/111739
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)⑤
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/22/203459
挿入BGM
YouTube Audio Library
From Here on In
挿入映像
映画インターステラーを参考用として一部を引用しています。
(c)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「映画」インターステラー
https://www.warnerbros.co.jp/home_entertainment/k4hjvhjawk2/
解説
1. 『インターステラー』の映像はなぜ画期的だったのか?
2014年に公開されたクリストファー・ノーラン監督の映画『インターステラー』は、壮大な親子の物語であると同時に、科学に忠実なSF作品として大きな注目を集めました。
この映画の科学的正確性を支えたのが、監修を務めた物理学者のキップ・ソーン博士です。彼の指導のもと、VFX制作会社のダブルネガティブ(DNEG)は、この映画のために**「Double Negative Gravitational Renderer(DNGR)」**という特別なレンダラー(画像生成ソフトウェア)を開発しました。
通常のCGは、光がまっすぐ進む「幾何光学」に基づいていますが、ブラックホールのような強大な重力を持つ天体の周りでは、空間そのものが歪み、光も曲がって進みます。DNGRは、この一般相対性理論の効果を計算に取り入れた画期的なものでした。この技術により、通常は見えないはずのブラックホールの裏側が見えるといった、驚異的な映像の制作が可能になったのです。
2. ブラックホールの物理シミュレーション
この映画の映像制作手法にインスパイアされ、同様のシミュレーションを自作で試みることができます。
基本的なアイデアは、CGで通常行われる光の直進計算を、重力場で湾曲する光の経路、すなわち**「null測地線」の計算に置き換える**というものです。映画で描かれているのは自転する「カーブラックホール」であり、その計算は複雑ですが、ルンゲクッタ法のような古典的な数値計算法を用いて解くことが可能です。
この結果が正しいか検証するため、DNEGが公開しているテスト画像と比較します。背景は異なりますが、高速で自転するブラックホールが回転対称にならずに歪んで見える様子など、非常に近い結果が得られていることがわかります。降着円盤(ブラックホールの周りにあるガスや塵の円盤)は、DNEGが粒子を飛ばして正確に計算しているのに対し、こちらではテクスチャを用いて簡略化していますが、全体としては正しく計算できていると考えられます。
3. ワームホールの可視化と「球体の穴」の意味
ブラックホールの計算で用いた仕組みは、ワームホールの可視化にも応用できます。 遠く離れた2つの空間をワームホールで繋ぐと、このように向こう側の景色を覗き込むことができます。
劇中で、主人公のクーパーがワームホールを見て「球体の穴だ」と理解する印象的なシーンがあります。 私たちが紙に開けた穴を想像すると、ワームホールは「円」に見えそうですが、それは2次元の話です。3次元の宇宙空間に存在する穴は、あらゆる方向から向こう側の世界を覗くことができるため、「球体」として見えるのです。実際にシミュレーションでレンダリングしてみると、この「球体の穴」という表現が直感的に理解できます。
4. 映画のワームホール通過シーンは本当に正しかったのか?
映画では、宇宙船がワームホールの中をまるでトンネルのように進んでいくシーンが描かれています。しかし、物理シミュレーションの結果は、これとは全く異なるものでした。
トンネルのような描写にはならず、入り口と出口の景色が混ざり合うような不思議な見え方になりました。
この結果は、ドイツのCorvin Zahn博士が公開しているシミュレーションとも一致しており、計算の妥当性を示唆しています。
では、なぜ映画の描写はシミュレーションと異なるのでしょうか?
5. 結論:科学的正確性と「創造的解釈」
その答えは、キップ・ソーン博士自身の著書『The Science of Interstellar』や、制作陣の論文、インタビューの中にありました。
結論から言うと、**映画のワームホール通過シーンは、科学的な正確さよりも映像としての面白さを優先した「創造的な解釈」**だったのです。
キップ・ソーン博士によると、物理シミュレーションに忠実な映像は「短く退屈」で、映画的な迫力に欠けていました。ノーラン監督から「もっと興奮するものにしてほしい」という要望があり、VFXチームは物理シミュレーションの映像に**意図的な「解釈的エフェクト」**を加えることにしました。
具体的には、DNGRによるシミュレーション映像に、「空撮素材を元にしたエフェクト」や「レンズ効果」を重ね合わせることで、風景が流れて目的地に近づいていく**「移動の感覚」や「トンネル感」**を観客に分かりやすく伝わるように演出したのです。VFXスーパーバイザーも、「物理的に正確な旅の再現は、特にドラマチックなものではなかった」とコメントしています。
このように、『インターステラー』の映像は、ブラックホールの外観のように大部分は科学シミュレーションに忠実でありながら、ワームホール通過シーンのように、観客の体験を最大化するために科学とアートを融合させた、非常に巧みな映像表現だったと言えるでしょう。
Видео 「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)は本当にに科学的に正しい映像だったのか? канала Sanaxen
notebooklmが生成した動画と解説音声、ストーリーは概ね正しいですが勝手な解釈や端折った部分が散見していますので詳細は下記のブログ内容でご確認ください。
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)①
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/08/28/201509
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)②
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/11/105538
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)③
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/13/153234
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)④
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/17/111739
「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)⑤
https://cat-falcon.hatenablog.com/entry/2025/09/22/203459
挿入BGM
YouTube Audio Library
From Here on In
挿入映像
映画インターステラーを参考用として一部を引用しています。
(c)2014 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures. All Rights Reserved.
「映画」インターステラー
https://www.warnerbros.co.jp/home_entertainment/k4hjvhjawk2/
解説
1. 『インターステラー』の映像はなぜ画期的だったのか?
2014年に公開されたクリストファー・ノーラン監督の映画『インターステラー』は、壮大な親子の物語であると同時に、科学に忠実なSF作品として大きな注目を集めました。
この映画の科学的正確性を支えたのが、監修を務めた物理学者のキップ・ソーン博士です。彼の指導のもと、VFX制作会社のダブルネガティブ(DNEG)は、この映画のために**「Double Negative Gravitational Renderer(DNGR)」**という特別なレンダラー(画像生成ソフトウェア)を開発しました。
通常のCGは、光がまっすぐ進む「幾何光学」に基づいていますが、ブラックホールのような強大な重力を持つ天体の周りでは、空間そのものが歪み、光も曲がって進みます。DNGRは、この一般相対性理論の効果を計算に取り入れた画期的なものでした。この技術により、通常は見えないはずのブラックホールの裏側が見えるといった、驚異的な映像の制作が可能になったのです。
2. ブラックホールの物理シミュレーション
この映画の映像制作手法にインスパイアされ、同様のシミュレーションを自作で試みることができます。
基本的なアイデアは、CGで通常行われる光の直進計算を、重力場で湾曲する光の経路、すなわち**「null測地線」の計算に置き換える**というものです。映画で描かれているのは自転する「カーブラックホール」であり、その計算は複雑ですが、ルンゲクッタ法のような古典的な数値計算法を用いて解くことが可能です。
この結果が正しいか検証するため、DNEGが公開しているテスト画像と比較します。背景は異なりますが、高速で自転するブラックホールが回転対称にならずに歪んで見える様子など、非常に近い結果が得られていることがわかります。降着円盤(ブラックホールの周りにあるガスや塵の円盤)は、DNEGが粒子を飛ばして正確に計算しているのに対し、こちらではテクスチャを用いて簡略化していますが、全体としては正しく計算できていると考えられます。
3. ワームホールの可視化と「球体の穴」の意味
ブラックホールの計算で用いた仕組みは、ワームホールの可視化にも応用できます。 遠く離れた2つの空間をワームホールで繋ぐと、このように向こう側の景色を覗き込むことができます。
劇中で、主人公のクーパーがワームホールを見て「球体の穴だ」と理解する印象的なシーンがあります。 私たちが紙に開けた穴を想像すると、ワームホールは「円」に見えそうですが、それは2次元の話です。3次元の宇宙空間に存在する穴は、あらゆる方向から向こう側の世界を覗くことができるため、「球体」として見えるのです。実際にシミュレーションでレンダリングしてみると、この「球体の穴」という表現が直感的に理解できます。
4. 映画のワームホール通過シーンは本当に正しかったのか?
映画では、宇宙船がワームホールの中をまるでトンネルのように進んでいくシーンが描かれています。しかし、物理シミュレーションの結果は、これとは全く異なるものでした。
トンネルのような描写にはならず、入り口と出口の景色が混ざり合うような不思議な見え方になりました。
この結果は、ドイツのCorvin Zahn博士が公開しているシミュレーションとも一致しており、計算の妥当性を示唆しています。
では、なぜ映画の描写はシミュレーションと異なるのでしょうか?
5. 結論:科学的正確性と「創造的解釈」
その答えは、キップ・ソーン博士自身の著書『The Science of Interstellar』や、制作陣の論文、インタビューの中にありました。
結論から言うと、**映画のワームホール通過シーンは、科学的な正確さよりも映像としての面白さを優先した「創造的な解釈」**だったのです。
キップ・ソーン博士によると、物理シミュレーションに忠実な映像は「短く退屈」で、映画的な迫力に欠けていました。ノーラン監督から「もっと興奮するものにしてほしい」という要望があり、VFXチームは物理シミュレーションの映像に**意図的な「解釈的エフェクト」**を加えることにしました。
具体的には、DNGRによるシミュレーション映像に、「空撮素材を元にしたエフェクト」や「レンズ効果」を重ね合わせることで、風景が流れて目的地に近づいていく**「移動の感覚」や「トンネル感」**を観客に分かりやすく伝わるように演出したのです。VFXスーパーバイザーも、「物理的に正確な旅の再現は、特にドラマチックなものではなかった」とコメントしています。
このように、『インターステラー』の映像は、ブラックホールの外観のように大部分は科学シミュレーションに忠実でありながら、ワームホール通過シーンのように、観客の体験を最大化するために科学とアートを融合させた、非常に巧みな映像表現だったと言えるでしょう。
Видео 「映画」インターステラーと物理シミュレーション(レンダラー)は本当にに科学的に正しい映像だったのか? канала Sanaxen
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
5 октября 2025 г. 20:00:26
00:05:26
Другие видео канала